手計算でもできる!
複式簿記を取り入れて家計管理をしてみよう!
大切なのは純資産で、家計の健康体力を見ていくこと!
っと、いう記事の中締めのまとめです。
これまでの記事↓
このブログのテーマは
今の生活を大切に楽しみながら
悠々自適な生活を目指して
やるべきことを実践する
これをする過程で、家計をしっかり管理する必然ができました。
そして、自分も含めて

家計簿つけているけど、お金の管理これでいいのかしら・・・

家計管理したいけど、やり方がわからないなあ・・・
こういう人たちのために書いています。
家計管理の目的とは?_「お金の不安をなくすこと」!
正直、「管理」と名の付くものはめんどくさいものです。

なぜ、こんなめんどくさいことやっているんだろう・・・
こう思うことが度々ありました。
ですが、この記事を書き進めていくうちにわかったことがあります。
なぜ家計管理が必要なのか?
その答えに最も的確な言葉は、
” 不安 ”
人は誰しも幸せで安心安全の生活を求めて頑張ります。
ですが、「お金の不安」というのは、なかなか解消することができません。
年収300万で幸せを感じる人もいれば、
年収1000万でお金に関する不安がつきない人もいます。
なので、家計管理することの目的を 明確に
「お金の不安をなくすこと」!
こう言い切ってよいと思っています。
家計管理で把握したい3つのこと
なぜなぜを繰り返します。
では、なぜ、「お金の不安が生じるのか?」を考えてみました。
(※ここでいう「お金の不安」とは、年収が多い少ないの話ではありません)
これも記事を書いている過程で、はっきりしたものになっていきました。
- いくら持っているのかわからない
- 必要生活費がわからない
- 幸せ金額(ゆとり費)が設定できない
「わからない」 っという不安です。
と、いうことは、この3つをしっかり把握すれば、
お金について「安心」や「自信」が持てるのでは⁉
こう、考えます。
(※もう一度付け加えます、年収が多い少ないの話ではありません)
- いくら持っているのかを把握する
「わたし、いったいいくら持っているんだろう?・・・」
当然、このような人は不安ですよね・・・。- あなたはいくら資産を持っていますか?
- 純資産はいくらありますか?
このような自問自答をしたとき、すぐにその回答ができるようになっておきたいものです。
- 必要生活費を把握する
「僕はいくらあれば生活できるのだろう?・・・」
この「必要生活費」という言葉には「最低」という意味を含みます。
人の環境は千差万別、
「自身の最低限の生活を維持するお金」を把握しておくと安心ですよね。 - 幸せ金額(ゆとり費)を設定する
「必要生活費」を把握したうえで、
「幸せに暮らす、ゆとりある生活」をするには、〇✕万円必要だ!
っと、いうのがわかれば、明確な目標値が設定されて、
漠然とした不安から解消されることでしょう。
複式簿記を取り入れた【家計管理】を行えば、この3つを把握するデータがすべてそろうことになります。
把握した3つを思案する
とは、いったものの、
時間を止めて、この3つをしっかり把握しておけばいい、というものではありません。
時間は流れ、そして生活環境と自身の感情は変化していくからです。
要は、
「この3つを把握するデータ」を持っておくこと!
これが大事だと思うんです!
このために複式簿記を取り入れた【家計管理】が必要なのです。
じーっと、【家計管理】データをみつめ、把握したい3つについて思案します。
創意工夫で次のステップ
さらに思案の深度を深めていくと、いろんなことを思うようになります。
- 純資産を増やす方法はないか?
- 節税対策できないか
- 年末調整、確定申告等の税制知識
- ふるさと納税、iDeco等の公的制度の活用
- 投資運用
- 安全に資産を運用する方法はないか
- 負債勘定の検討
- いい負債?悪い負債?負債について考える
- いい負債?悪い負債?負債について考える
- 節税対策できないか
- 必要生活費を下げることはできないか?
- もっと節約できないか_固定費を下げる検討
- 変動費に対する対応_無駄使いの要素はないか
- 有効なお金の使い方をしているか_ゆずれることと、ゆずれないこと
- ゆとりある生活を送るには?
- 将来発生する費用を予測してみる
- 目標をもって資金計画を策定する
- 効率のいいお金の使い方で悠々自適プランを考える
思案の深度は深まるばかりですね。
少し話がそれたかもしれません。
このシリーズは複式簿記を取り入れた【家計管理のススメ】です。
【家計管理】データをじーっとみながら思うこと、
ピン! っと、きました。
将来発生する費用を予測して
対処することができないか!
このことについて、もう少し深堀、展開していこうと思っています。
中締めのまとめ
ここまでの記事
これまで、家計簿をつけている中年サラリーマンの奥さんをイメージして書いてきました。
ここまで順に読み進んでこられた方は、簿記の基本にふれたことになります。
はじめは面倒に思うことでしょう。
できるだけ、管理する「勘定科目」を少なくして、まずは精算表を作るところまで頑張ってみてください。
さて、「中締めとしてのまとめ」は終わりにします。
「中締め」なので、まだ続くということです。
次のステップ、
「こんな考えをして現状を把握してはどうだろう!・・・」
応用編として、こんな記事を書こうと思っています。
「将来発生する費用を予測して対処することができないか!」
主に「負債勘定」についての話になります。
では!

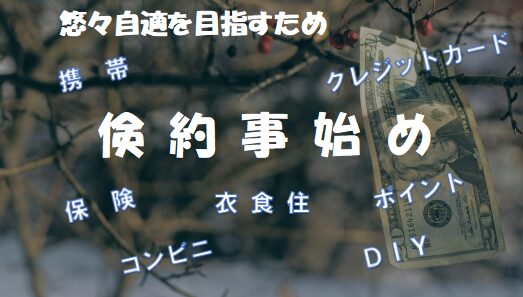
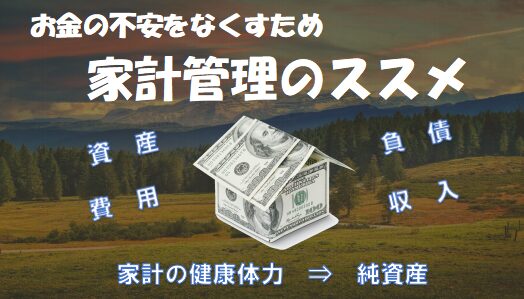
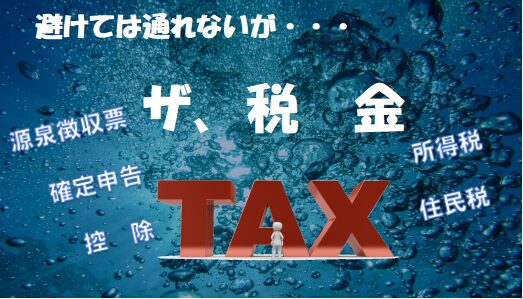
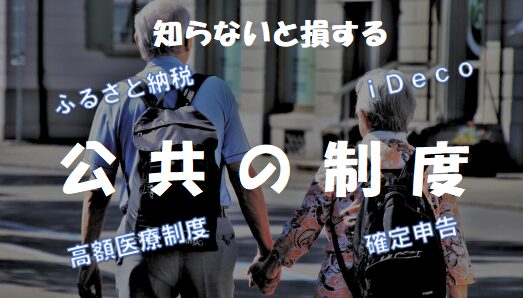
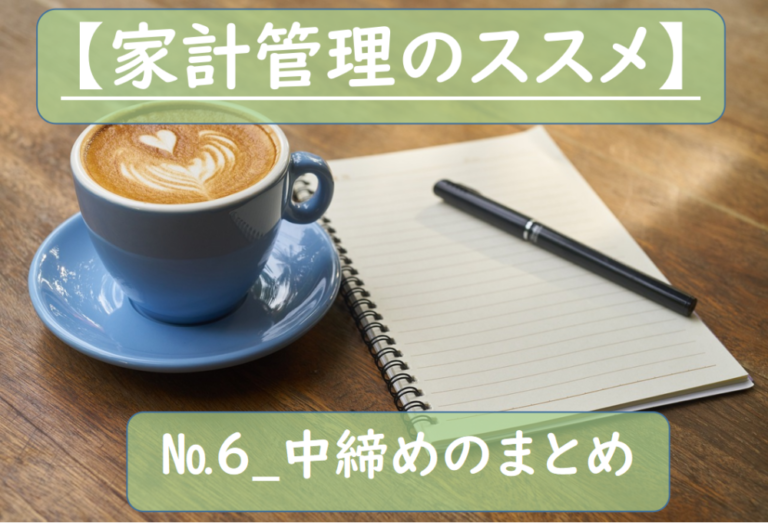
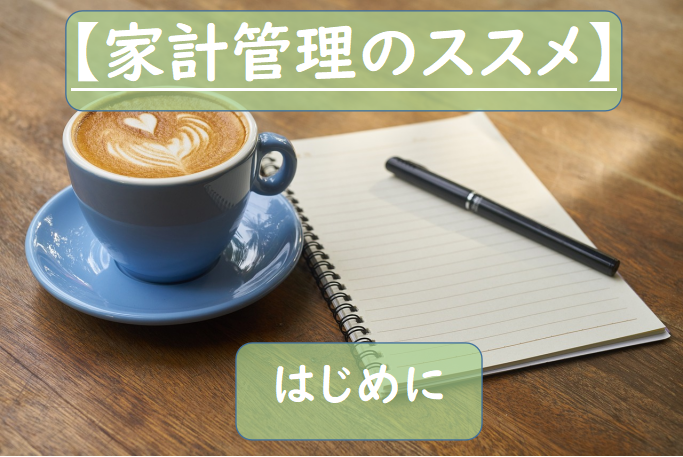
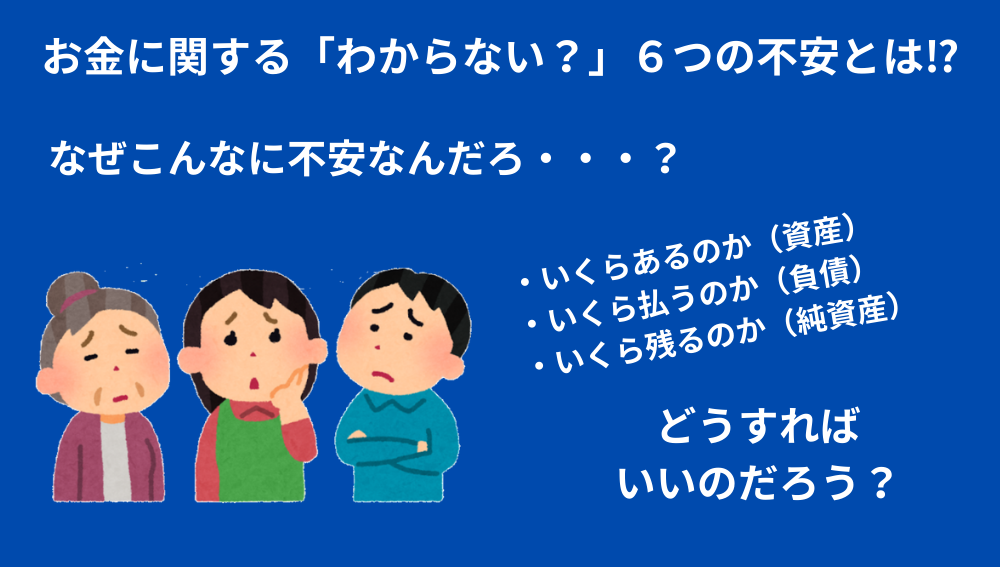
コメント